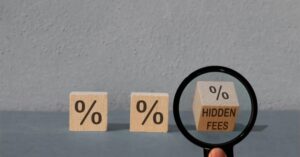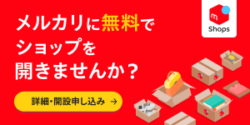食品メーカーとして、自社の商品をネットショップで販売したいけれど、何から始めればいいか迷っていませんか?この記事では、ネットショップ開設の準備から、ECモールを活用した最適な販売方法までを分かりやすく解説します。
食品メーカーがネットショップを始める前に知っておくべきこと

食品ECで成功するには、市場動向の把握と自社に合う販売チャネル選択が欠かせません。闇雲に開設するのではなく、ECモールと自社ECの違い、必要な法令対応や運営体制を理解することで、リスクを抑えつつ着実に成長できます。まずはじめに、ECモールと自社EC両チャネルの特徴と、食品ECの最新動向、お客さまとなる消費者が重視するポイントを整理します。
ネットショップ開設の選択肢:ECモールか自社ECサイトか
ネットショップには大きく分けて、メルカリShopsをはじめ、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングといったECモールと、自社で構築するオリジナルのECサイトの2つの選択肢があります。
ECモールは大型商業施設のように複数の店舗が集まる仕組みで、すでに多くの利用者が集まっているため、販売開始直後から商品を見てもらいやすいのが特徴です。
一方、自社ECサイトはデザインや機能を自由に設定でき、ブランドの世界観を表現しやすい反面、集客は自力で行う必要があり、運営コストもかかります。
それぞれの特徴とメリット・デメリット
ECモールの最大のメリットは、モールの持つ集客力の高さにあります。
ECモールとは、多くの店舗が軒を連ねるオンライン上の商業施設のようなものです。すでに多くの利用者が集まるプラットフォームであるため、新規のお客さまにも商品を見つけてもらいやすく、販売開始直後から売上を上げられる可能性があります。
また、決済や配送システム、お客さまサポートの仕組みがすでに整っているため、専門的な知識がなくても比較的スムーズに運営を始められます。
一方で、注意すべき点としては、モール側に支払う出店料や販売手数料、システム利用料などが発生する点です。また、モール内の規約に縛られるため、自由なブランディングやデザインは難しく、他社との価格競争に巻き込まれやすいという側面もあります。
一方の自社ECサイトは、デザインや世界観を自由に表現できるため、商品の魅力を最大限に伝え、顧客との長期的な関係を築きやすいのが大きなメリットです。手数料を支払う必要がないため利益率を高めやすく、顧客データを自社で管理できる点も強みです。
ただし、集客は自社で行わなければならず、広告やSEO対策が必要になります。さらに、サイト構築やセキュリティ対策などに専門知識とコストがかかる点は大きな課題です。
食品メーカーがECで成功するための鍵
食品ECで成功するためには、「美味しさ」と「安心」をどのように伝えるかが重要です。写真や動画で商品の魅力を伝えることに加え、生産者の想いや製造過程をストーリーとして発信することで共感を生みやすくなります。
また、原材料、アレルギー情報、賞味期限や保存方法などを正確に明示することで、安心感を提供できます。
さらに、温度管理を徹底した配送体制や、トラブル発生時の迅速な対応も信頼獲得に欠かせません。
EC市場の現状と食品メーカーに求められること
食品EC市場は、新型コロナ禍を契機に急速に拡大し、今では多くの消費者にとって当たり前の購買手段になりました。共働きや単身世帯の増加により、手軽に食品を購入したいニーズも高まり、市場は成長を続けています。
しかし競争も激化しており、ただ商品を並べるだけでは選ばれません。品質はもちろん、消費者にどのような体験や価値を提供できるかが問われています。
拡大を続ける食品EC市場の動向
従来は一部の層に限られていた食品ECも、今では生鮮食品や冷凍食品、ミールキットの需要が高まり、幅広い層に浸透しています。
また、地方の特産品やオーガニック食品など付加価値の高い商品を求める消費者も増え、価格よりも品質やストーリーに共感して購入するケースが増加しています。
さらに、サブスクリプション型の定期購入やパーソナライズされたレコメンド機能など、利便性を高める仕組みも拡大しており、市場は多様化・進化を続けています。
消費者がネットショップに求める「美味しさ」と「安心」
消費者が食品ECで重視するのは「美味しさ」と「安心」です。
美味しさは高品質な写真や動画、レビューなどで具体的に伝える必要があります。調理例や試食レポートを掲載することで、味を想像しやすくなり購買意欲を高められます。
一方、安心感を与えるには、食品表示法に基づいたアレルギー表示や原材料表示、製造工程や衛生管理の公開など、透明性のある情報提供が不可欠です。
さらに、冷蔵・冷凍配送や丁寧な梱包により、商品が安全に届くことを保証することも、リピーター獲得につながります。
食品メーカーにおすすめ!ネットショップ開設に向けた準備と手順
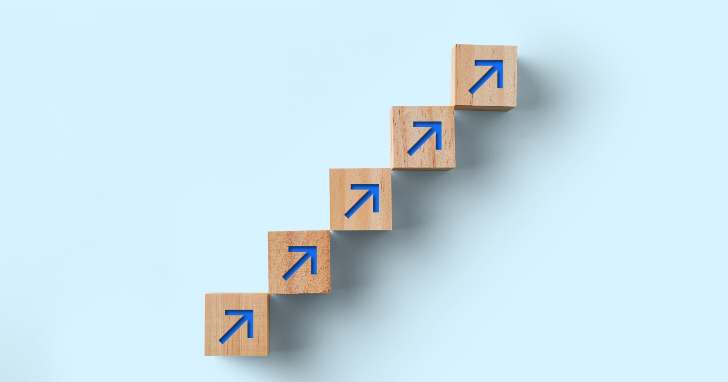
食品メーカーがネットショップを開設し、成功を収めるためには、事前の準備が欠かせません。単に商品を並べるだけでは競争の激しいEC市場では埋もれてしまいます。まずはネット販売に適した商品を選定し、ターゲット顧客や販売目標を明確にします。そのうえで、法律や資格といった必須条件を確認し、注文から配送までを円滑に行う運営体制を整えることが重要です。
ここからは、ネットショップ開設に向けた具体的なステップを順に解説します。
ステップ1. 販売する食品の選定と事業計画
ネット販売を始める際、最初に行うべきは「どの商品を誰に売るのか」を明確にすることです。自社のラインナップの中からオンライン販売に向いた商品を厳選し、ターゲット層を設定することで、効果的なマーケティング戦略を立てやすくなります。
健康志向の消費者に向けたオーガニック食品や、贈答需要を狙った高級商品など、販売コンセプトを絞り込むと競合との差別化につながります。また、販売目標や収支計画を立てることで、必要な販売数やコストが明確になり、事業を継続的に伸ばすための指針になります。
ネットで売れる食品・売れにくい食品の特徴
ネット販売に適した食品にはいくつかの共通点があります。缶詰やレトルト食品、乾物、調味料、お菓子などのように日持ちがし、輸送中のリスクが低い商品は売れやすい傾向にあります。
また、地域限定の特産品や期間限定商品、オーガニック食品など、特別感のある商品もオンライン販売に向いています。
一方、傷みやすい生鮮食品や単価の低い日用品は、送料とのバランスが取れず売りにくい・また利益が残りにくいケースもあります。その場合は、セット販売や付加価値を付ける工夫が必要です。
ターゲット顧客と販売目標の設定
成功するネットショップには明確なターゲット設定が欠かせません。
たとえば「健康意識の高い30代女性」「共働きの子育て世帯」「食にこだわるシニア層」といった具体的なペルソナを描くことで、商品ページや広告の内容を最適化できます。
さらに、月商や年間売上といった数値目標を設定し、逆算して必要な販売数や広告費を見積もることで、実行可能な事業計画を立てられます。
ステップ2. 食品販売に必要な法律・ルールの確認
食品を販売する事業者は、消費者の安全を守るためにさまざまな法律を遵守する義務があります。
食品衛生法や食品表示法といった基本法規はもちろん、販売する食品の種類によっては追加で許可や資格が必要になる場合もあります。
これらを事前に確認しておくことが、法的トラブルを回避し、安心して運営を続けるための基盤になります。
食品衛生法や食品表示法など、遵守すべき法律の基礎知識
食品衛生法は、食品の安全を確保するために定められた法律で、施設の衛生管理や製造・販売の基準を規定しています。
食品表示法では、アレルゲン、原材料、賞味期限や保存方法、栄養成分などを正確に表示することが義務付けられています。
特にアレルギー情報は消費者の命に直結するため、誤りのない表示が不可欠です。
さらに健康増進法や特定商取引法、計量法など関連法規も多岐にわたり、違反すれば罰則だけでなく信頼を失うリスクがあります。
食品衛生責任者などの資格・許認可の確認
食品を扱う事業者の多くには「食品衛生責任者」の配置が求められます。自治体が実施する講習を受講すれば取得でき、施設内の衛生管理を担います。また、菓子やパンの製造、食肉や乳製品の販売など、取り扱う商品によっては営業許可が必要です。
保健所が施設基準を確認したうえで許可を出すため、事業開始前に必ず相談しておくことが大切です。
ステップ3. 運営体制と必要なリソースの確保
ネットショップ運営は、商品の選定や法律遵守だけでなく、日々のオペレーション体制が重要です。注文から発送までを効率的に回す仕組みを整え、在庫管理や梱包、配送、顧客対応のプロセスをあらかじめ設計しておきましょう。役割分担を明確にすることで、運営開始後のトラブルを防げます。
商品企画・生産・在庫管理
安定した供給体制はEC事業の土台です。
商品企画段階では、限定品やセット販売などネット向けのラインナップを検討します。生産体制では注文数に応じて柔軟に対応できる仕組みを整え、在庫管理では先入れ先出しを徹底し、賞味期限切れや過剰在庫を防ぐ必要があります。
自動で在庫を同期できるシステムや定期棚卸しを導入すると効率が高まります。
梱包・配送(クール便対応)とカスタマーサポート
食品販売では配送品質が信頼を左右します。冷蔵・冷凍商品はクール便を必ず利用し、保冷剤や緩衝材で品質を保持しましょう。配送状況を追跡できる仕組みも導入するとお客さまの安心感が高まります。さらに、お客さまからの問い合わせやトラブルに迅速に対応できるサポート体制を構築することが、リピーター獲得につながります。
FAQやチャットボットを活用して一次対応を効率化するのも有効です。
食品メーカーがECモールを活用すべき理由とメリット

食品メーカーにとってECモールへの出店は、スピーディーに事業を立ち上げられる有力な選択肢です。
モールにはすでに多くの利用者が集まっており、ゼロから集客する必要がないため、立ち上げ初期の大きな助けとなります。特に食品は安全性が重視されるため、消費者が信頼するプラットフォームに出店することは販売促進に直結します。
ECモールが食品販売におすすめな理由
ECモールが食品販売に適している理由は大きく「集客力」「運営の容易さ」「信頼性」の3点にまとめられます。
大手モールには毎日膨大な数の利用者が訪れるため、商品を見てもらえる機会が格段に増えます。さらに、決済や配送システムが整っており、出店者は販売活動に集中できます。
モール自体が持つブランド力は、特に高単価商品を販売する際の安心材料となり、購入を後押しします。
多くのユーザーに商品を見てもらえる集客力
メルカリShops、楽天市場やAmazonなどのECモールには月間数千万人規模のユーザーが訪れており、自社ECでは到達が難しい潜在顧客に商品を届けられます。
検索機能や特集ページを通じて露出機会を増やせるため、販売初期から売上を立てやすいのが特徴です。
プラットフォーム側で決済や配送システムが整っていて運用がスムーズ
モールに出店すれば、クレジットカードやコンビニ決済などの支払い方法が標準で利用可能です。さらに、提携配送サービスを通じて手間なく出荷でき、システム構築にかかる時間や費用を削減できます。
プラットフォーム自体の信頼性で高単価商品でも売れやすい
食品購入では安全性や確実に届くかどうかが重要です。信頼性の高いモールはセキュリティや取引保証が整っているため、消費者が安心して購入できます。
特にギフトや高価格帯の商品販売においては、この安心感が大きな強みとなります。
ECモール活用のデメリットと注意点
モールには手数料が発生し、利益率が低下しやすい点は注意すべきポイントです。また、多数の競合店舗が存在するため価格競争に陥りやすく、ブランドを前面に打ち出すのが難しいという課題もあります。そのため、商品の強みやストーリー性で差別化を図ることが求められます。
手数料、ブランド構築の難しさ、競争激化などの注意点
モールでは販売額に応じて手数料が差し引かれるため、価格設計を誤ると赤字になりかねません。さらに、モール内では「メルカリで買った」「楽天で買った」「Amazonで買った」と認識されやすく、ブランド独自の印象を残しにくい傾向があります。
同様の商品を扱う店舗が多いため、単に価格で勝負するのではなく、付加価値や顧客対応で差をつける戦略が必要です。
出店先選びに便利!主要ネットショップ(ECモール)の特徴と概要

ECモールに出店しようと考えても、選択肢が多いとどこを選べばいいかわからない・また、モールごとにいくら費用がかかるのかが知りたいという方も多いでしょう。
ここでは、代表的なネットショップ出店サービスを比較しやすいよう一覧化したものをご紹介します。出店先選びの参考にぜひご活用ください。
| プラットフォーム名 | 出店登録費用 | 別途手数料 |
|---|---|---|
| メルカリShops | 無料 | ・売上金の10%が販売手数料 ・販売利益の振込時、1回につき200円の振込手数料 |
| 楽天市場 | ・がんばれ!プランの場合:25,000円/月額(年間一括払) ・スタンダードプランの場合:65,000円/月額(半年ごとの2回分割払) ・メガショッププランの場合:130,000円/月額(半年ごとの2回分割払) 【全プラン共通必須費用】 初期登録費用:60,000円 楽天ポイント:楽天会員の購入代金(税抜)×付与率(通常1.0%) 楽天スーパーアフィリエイト:アフィリエイト経由売上の2.6~5.2% モールにおける取引の安全性・利便性向上のためのシステム利用料:月間売上高の0.1% R-Messe:月額固定費(税別) がんばれ!プラン:3,000円 スタンダードプラン・メガショッププラン:5,000円 (2025年9月29日現在無料期間中(終了時期未定)です。) 楽天ペイ利用料:月間決済高の2.5%~3.5% 上記の料金はすべて税別です。 | ・がんばれ!プランの場合:システム利用料 パソコン/3.5%~6.5%、モバイル/4.0%~7.0% ・スタンダードプランまたはメガショッププランの場合:システム利用料 パソコン/2.0%~4.0%、モバイル/2.5%~4.5% |
| Amazon | ・大口出品の場合:4,900円/月 ・小口出品の場合:100円/商品 | ・商品カテゴリーによって異なる(多くの場合は5%~15%の販売手数料) |
| Yahoo!ショッピング | 無料 | ・ストアポイント原資負担:1%~15%(現在1%は必須になります) ・キャンペーン原資負担 :1.5% ・アフィリエイトパートナー報酬:1%~50%(1%は必須) ・アフィリエイト手数料:アフィリエイトパートナー報酬の30% ・ストア決済サービス手数料:決済方法により異なります ・売上金振込依頼1回につき100円(税込)ただしPayPay銀行口座への振込手数料は無料 |
| Shopify | ・Basic:4,850円/月 ・Grow:13,500円/月 ・Advanced:58,500円/月 ・Plus:$2,300/月(3年契約) ※一部のプランにおいて年払いの場合は25%オフが適用されます | Shopifyペイメント・Shopifyペイメントを使用しない場合の外部サービス取引手数料・Shopify Marketplace Connectにおける手数料・その他の有料サービスなど利用状況に応じた手数料の発生 |
| STORES | ・フリープラン:無料 ・ベーシックプラン:3,480円/月 | ・フリープランの決済手数料:5.5%〜 ・ベーシックプランの決済手数料:3.6%〜 ・振込手数料:売上合計が1万円以上の場合は275円・売上合計が1万円未満の場合は275円に加え事務手数料275円 |
| eBay | 月額ストア費用(年間契約):ストアなし0USD/月・スターターストアプラン4.95〜USD/月・ベーシックストアプラン21.95〜USD/月・プレミアムストアプラン59.95〜USD/月・アンカーストアプラン299.95〜USD/月・エンタープライズストアプラン2,999.95〜USD/月 | ・出品手数料(無料出品枠超):ストアなし0.35$/1品・スターターストアプラン0.30$/1品・ベーシックストアプラン0.25$/1品・プレミアムストアプラン0.1$/1品・アンカーストアプラン&エンタープライズストアプラン0.05$/1品 ・海外決済手数料:全プラン共通0.4%〜1.35%(先々月の総売上金額によりディスカウントあり) |
| Qoo10 | 無料 | ・カテゴリー別に6〜10%の販売手数料(決済手数料込み)※「メガ割」時の対象商品は購入決済金額のプラス1%/Qoo10負担割引が適用された注文はプラス0.5%/予約販売、後日配送の場合はプラス2%/Qoo10での銀行口座登録が日本国外の場合、または商品出荷地が日本国外の場合はプラス2%/Qoo10サイト以外の外部広告、または最安値コーナー経由の売上の場合はプラス1% ・販売利益の振込時、1回につき150円の振込手数料 |
記載の情報は2025年9月現在の情報です。最新の情報は各社公式ページにてご確認ください。
メルカリShops:ネットショップひらくならメルカリShops (ショップス)
楽天市場:出店プランと費用|楽天市場
Amazon:料金プラン、配送手数料、料金シミュレーター | Amazon出品サービスの料金
Yahoo!ショッピング:料金・費用|ネットショップ開業ならヤフーショッピング
Shopify:Shopifyの料金プラン – 各プランの詳細情報と比較 – 無料体験 – Shopify 日本
STORES:利用料金・手数料 | STORES ネットショップ
eBay:料金について
Qoo10:Qoo10大学 |費用
ネットショップを開設したい食品メーカー様にはメルカリShopsへの出店がおすすめ!その理由は?
ネットショップを開設したいとお考えの食品メーカー様におすすめしたいのが、メルカリShopsへの出店です。
メルカリShopsなら、集客力や配送体制、料金体系の分かりやすさなど、食品販売をしやすい環境が揃っており、オンラインでの販売先を探している方はもちろん、新規事業立ち上げにも適しています。
ここから、メルカリShopsの出店をおすすめしたい具体的な理由についてご紹介・解説していきます。
月間約2,300万人がお買い物を楽しむフリマアプリ「メルカリ」の市場へネットショップを出店できる
メルカリShopsに出店すると、月間約2,300万人が利用するフリマアプリ「メルカリ」の巨大な市場に商品を掲載できます。
自社でゼロから集客する必要がなく、立ち上げ直後から多くのユーザーに商品を見てもらえるチャンスが生まれます。
冷凍・冷蔵商品をお得に発送できる独自の配送サービス「クールメルカリ便」で配送コストを抑えられる
メルカリShopsには「クールメルカリ便」という独自の配送サービスがあります。
クールメルカリ便は、ヤマト運輸と提携しており、冷蔵・冷凍商品を全国どこへでもサイズ別の一律料金で送ることができます。そのため、食品メーカーは配送コストを抑えながら、地域によるコスト差を気にせず全国に商品を販売できます。
💡:クールメルカリ便の利用方法 – メルカリShopsガイド
食品・飲料・酒カテゴリーの流通総額は約1.25倍に成長!売れやすい環境が整っている
メルカリShopsの食品・飲料・酒カテゴリーは、前年比約1.25倍と成長しています。(※調査詳細:2024年3月月間と2025年3月月間の売上比較)また、同カテゴリーは人気カテゴリーBest3(2024年3月1日〜2025年3月31日における累計売上実績)にも入っています。
このデータからも、フリマアプリ「メルカリ」を利用するお客さまが、メルカリShopsの出店者から食品のお買い物を楽しむ方が増えてきていることを示しており、食品メーカーにとって新規参入しやすい環境があります。
出店料無料から始められるため、新規事業のリスクを最小化できる
メルカリShopsは出店料・初期費用が無料で、商品が売れるまでは手数料が生じず、商品が売れたときにはじめて手数料が発生する仕組みです。
初期費用がかからないため、まずは小規模に販売を試し、お客さまの反応を見てから事業拡大を検討したいという方にも気軽にご利用いただけます。
甲羅組様をはじめとした大手法人から小規模事業者様による出店実績が多数
メルカリShopsには、大手法人から個人経営の小規模事業者まで幅広い出店実績があります。
メルカリShopsアワード2023上半期「食品・飲料部門」で1位を受賞した「甲羅組」様は、メルカリShopsの魅力について、「簡単に出店できることと、メルカリの売上金で商品が購入できるところが魅力的だった」とお話いただいております。
💡:メルカリShopsアワード2023上半期「食品・飲料部門」1位受賞!売上UPの秘訣は徹底したお客さま目線。「甲羅組」さん|メルカリびより【公式サイト】
また、「食肉流通センターのお肉屋さん」様では、フードロスを減らしたいという思いで、ネットショップでお肉を取り扱うことを考え、メルカリShopsに出店いただきました。
「メルカリ自体がすごく有名で、利用者も多いので売り上げが見込めるなと思いました。以前からフリマアプリ「メルカリ」は使っていたのですが、操作がすごくかんたんだったのも決め手になりました。」「モールによっては操作が複雑で手間取ることもあるんですが、メルカリを使った経験からメルカリShopsはおそらくサクサク操作できるだろうなと期待して始めました。実際、すごくかんたんでした。」とお話いただいております。
💡:運営1人で月商1,000万円超!飲食店からネットショップへ業態転換し、フードロスに取り組む。「食肉流通センターのお肉屋さん」
売上を後押しする便利な販促サービスを無料で活用できる
メルカリShopsでは、時間限定で価格を設定し訴求・販売できるタイムセール機能や、ショップをフォローいただいたお客さま限定でクーポンを発行できる機能など、売上アップにつながる様々な販促機能を無料で利用できます。
EC一元管理システムとAPI連携しているため販路拡大もスムーズに実現可能
すでに他のECモールや自社ECサイトを運営している場合でも、メルカリShopsは主要な一元管理システムとAPI連携が可能です。
EC一元管理システムを利用することにより在庫や受注を一括で管理でき、在庫切れや二重販売といったトラブルを防ぎながら効率的に販路を拡大できます。
ネットショップで食品を売るための成功戦略

食品のネット販売で成果を上げるためには、商品の魅力を正しく伝えるページ作りと、効果的なプロモーション戦略が欠かせません。実店舗では味や香りで訴求できますが、ネットでは写真・動画・文章を駆使して「美味しさ」と「安心」を届ける必要があります。
美味しさと安心を伝える商品ページ作成術
食品の商品ページは「オンラインの試食会」とも言える重要な役割を担います。
高品質な写真や動画、商品のこだわりを伝える文章、正確な情報表示を組み合わせることで、お客さまに具体的なイメージを持ってもらえます。
製造過程や原材料のこだわりなど商品の魅力を最大限に伝える写真
食品の商品ページにおいて、写真はもっとも重要な要素のひとつです。
お客さまはまず視覚情報から商品の価値を判断します。盛り付け例や断面写真に加え、収穫や製造の様子、原材料の鮮度が伝わる写真を掲載することで、商品のこだわりを効果的に表現できます。
複数の角度やサイズ感がわかる写真を用意することで、購入前の不安を軽減し、購買意欲を高められます。
商品の魅力を引き出すキャッチコピーとストーリー
写真と並んで重要なのがキャッチコピーと商品ストーリーです。
商品の特徴を端的に伝えるキャッチコピーは、お客さまの興味を引くきっかけになります。さらに、生産者の想いや開発の背景、製造工程に込められたこだわりをストーリーとして伝えることで、単なる「商品」ではなく「体験」として認識してもらえます。
これにより、購入の動機付けやリピーター獲得につながる可能性が高まります。
アレルギー表示や栄養成分表示など、安心材料を丁寧に記載
食品販売において欠かせないのが「安心感」です。
アレルギー情報、原材料名、栄養成分、保存方法、賞味期限などは、法律に基づき正確に表示する必要があります。特にアレルギー表示は命に関わる情報であるため、誤りのないよう細心の注意を払いましょう。
また、食品添加物の有無や製造工場の衛生管理体制などを明記することで、さらに信頼性を高めることができます。
ネットショップ運営を成功に導くプロモーション戦略
ネットショップを開設しただけでは、お客さまはなかなか集まりません。
商品の魅力を最大限に引き出す商品ページを作成した後は、積極的なプロモーション活動でお客さまを呼び込むことが重要です。
SNSを活用した情報発信や、期間限定のキャンペーン、クーポンの配布など、様々な手法を組み合わせることで、お客さまの関心を引きつけ、購買へと繋げられます。
ここでは、ネットショップの売上を伸ばすための効果的なプロモーション戦略について解説します。
SNSでレシピやアレンジ方法を発信し、顧客の関心を高める
SNSは、お客さまとのコミュニケーションを深め、商品の魅力を伝えるための強力なツールです。例えば、InstagramやTikTokでは、商品の調理動画や、アレンジレシピ、美味しそうな食べ方を発信することで、お客さまに「作ってみたい」「食べてみたい」と思ってもらえます。単に商品そのものを宣伝するだけでなく、商品を通じて得られる「食の体験」を伝えることがポイントです。
また、お客さまが投稿した商品写真やレビューをリポスト(シェア)することで、お客さまとのエンゲージメントを高め、コミュニティを形成できます。SNSを通じて、お客さまが商品をより身近に感じられるような情報発信を継続的に行うことが重要です。
キャンペーンやクーポンの配布でお客さまを呼び込む
期間限定のキャンペーンや、クーポン配布の実施は、新規のお客さまを呼び込み、売上を大きく伸ばすための効果的な手法です。
例えば、「初回購入限定10%オフクーポン」を発行したり、「期間限定で送料無料キャンペーン」を実施したりすれば、購入を迷っているお客さまの背中を押すことができます。
また、購入額に応じて割引を適用する「まとめ買いキャンペーン」は、客単価の向上にも繋がります。
これらのキャンペーンは、SNSやメールマガジン、ネットショップのトップページで大々的に告知し、お客さまの関心を高めることが重要です。
定期的にキャンペーンを実施することで、お客さまがネットショップを訪問するきっかけを作り、リピーターの獲得にも繋げられます。
食品メーカーがネットショップを運営する際の注意点

食品メーカーがネットショップを運営する際には、特有の注意点がいくつかあります。
実店舗以上に、お客さまとの直接的なコミュニケーションが限られるため、商品情報や品質管理、トラブル対応など、細心の注意を払う必要があります。
これらの注意点を事前に把握し、適切な対策を講じることで、お客さまからの信頼を損なうことなく、安定した事業運営を続けられます。
ここでは、食品販売に必須の法律遵守から、商品の品質管理、そして万が一のトラブルに備えるためのポイントについて解説します。
食品表示法など、食品販売に必須の法律を遵守する
食品をネットショップで販売する場合、食品表示法をはじめとする各種法律の遵守は最も重要な注意点です。
商品情報ページには、原材料名、アレルギー表示、賞味期限または消費期限、保存方法、内容量、製造者(または販売者)の名称・所在地などを正確に記載しなければなりません。これらの情報に不備があった場合、行政指導の対象となるだけでなく、お客さまからの信頼を失い、事業の継続が困難になる可能性があります。特に、アレルギー情報は、お客さまの健康に直結するため、二重三重の確認を徹底しましょう。
法律の改正など、常に最新の情報を入手し、適切な対応を続けることが重要です。
鮮度・品質管理と在庫管理の徹底
食品は、鮮度が命です。ネットショップでの販売では、商品の鮮度・品質を保ったままお客さまの手元に届けることが不可欠です。そのため、在庫管理と品質管理を徹底しましょう。
特に、賞味期限がある商品は、先入れ先出しを厳守し、廃棄ロスを最小限に抑えることが重要です。
また、冷蔵・冷凍食品を扱う場合は、倉庫や配送時の温度管理を徹底し、商品が最適な状態で保管・輸送されるように注意しましょう。
定期的に在庫状況を確認し、常に新鮮な商品を確保できる体制を整えることが、お客さまからの信頼獲得につながります。
配送時の品質保持(温度管理)と梱包
ネットショップで食品を販売する際、最もトラブルになりやすいのが配送時の品質保持です。お客さまが商品を受け取った際に、商品が溶けていたり、傷んでいたりすると、クレームにつながるだけでなく、リピーター獲得のチャンスを失ってしまいます。
そのため、冷蔵・冷凍商品は必ずクール便を利用し、保冷剤や緩衝材を適切に使い、丁寧な梱包を心がけましょう。
また、壊れやすい商品や、液漏れしやすい商品は、専用の梱包材を使用するなど、配送中の破損リスクを最小限に抑える工夫が必要です。
万が一のトラブルを想定しきちんと備える
どんなに注意深く運営していても、商品の配送遅延や、破損、注文間違いなど、万が一のトラブルは起こり得ます。
重要なのは、トラブルが発生した際に、いかに迅速かつ丁寧に対応できるかです。あらかじめ、返金・交換ポリシーを明確に定め、お客さまからの問い合わせ窓口を用意しておくことが重要です。
また、商品に不具合があった場合の対応マニュアルを作成し、担当者全員が同じ対応ができるようにしておきましょう。お客さまからのクレームは、事業改善のための貴重なフィードバックでもあります。真摯に対応することで、かえってブランドへの信頼を高められることもあります。
まとめ:最適なネットショップを活用して食品ビジネスを成長させよう

食品メーカーにとってネットショップは、事業成長の大きなチャンスです。ECモールと自社ECサイトの特徴を理解し、自社に合ったチャネルを選ぶことで効率的な販売が可能になります。
商品の美味しさと安心を伝える商品ページを作成し、配送や情報開示の徹底で信頼を築き、SNSやキャンペーンで継続的に顧客を獲得していけば、リピーターを増やし安定した売上が見込めます。ぜひ本記事が食品ECでの成功の一助になると幸いです。



![【V65_MS_752]ECにおける越境販売の基礎知識:メリットと注意点、始め方を徹底解説](https://jp-news.mercari.com/contents/wp-content/uploads/2025/01/名称未設定のデザイン-9-300x158.jpg)


![[V66_MS_754]リユースショップの通販展開:成功への道筋と実践ポイント](https://jp-news.mercari.com/contents/wp-content/uploads/2025/01/名称未設定のデザイン-16-300x158.jpg)